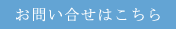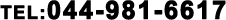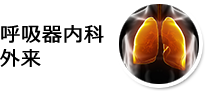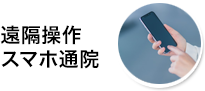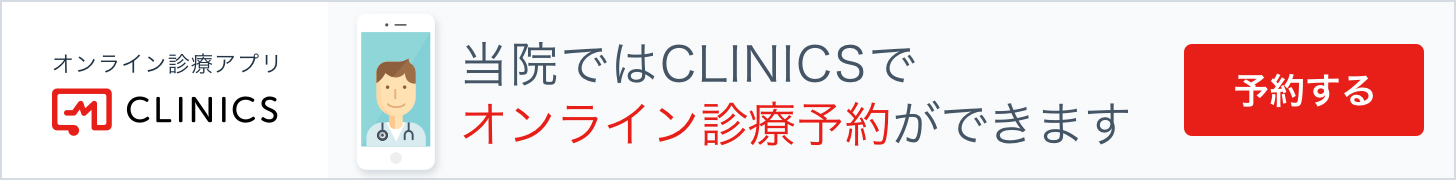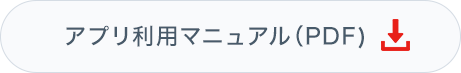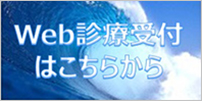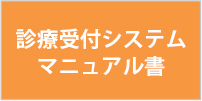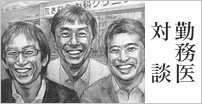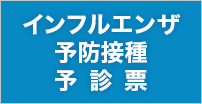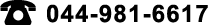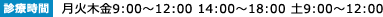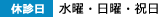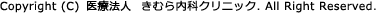クリニック便り
●2019年4月16日(火)
木村院長が、国連でスピーチを行いました!
去る2019年3月22日、国連ニューヨーク本部に於いて、「医療現場におけるトラウマについて」の英語スピーチを行いました。
国連の伝統的な委員会である「女性の地位委員会(CSW)」は今年で第63回目でした。毎年、その年のテーマに関して、各国のNGO女性リーダーや研究者たちが約2週間に渡って会議やセミナーを行って智慧を共有します。「女性が体験するトラウマ、恐怖について」というセミナーにおいて、ゲスト・スピーカーとして医師の立場で「医療現場におけるトラウマについて」という約20分間の英語スピーチを行いました。
医療現場でも、患者が信頼している“権威者”である医師の「言葉」によって、心に深く残る傷=トラウマは発生しており、そのことに医師はもっと注意を払うべきであり、患者自身に心と身体が密接に影響しあっていることを伝えていくことが必要であることを強く訴えました。スピーチの後で、世界各国の人から、多くの関心と共感のコメントを得ることができました。

●2019年3月1日(金)
木村院長が、The New York Times「Next Era Leader's」に選ばれました!
「人の心にフォーカスする医療を世界のスタンダードに」と題された、木村院長へのインタビュー内容を記載した記事が、The New York Timesの特設ウェブサイトに掲載されました。
当院の理念である、「心と身体を同時に癒し、病気を人生成功のチャンスに変える治療を世界のスタンダードにする」という熱いメッセージが、世界的に有名なメディアである、The New York Times誌の目に留まったことはとても嬉しいことです。
心と医療の未知なるフロンティアにどんどん踏み込んで、次の世代に本物の医療を遺していきたいと思います。
全文はこちらから
URL:https://www.neltimes.com/persons.php/kensuke_kimura/

The New York Times 「Next Era Leader's」日本語訳版
人の「心」にフォーカスする医療を世界のスタンダードに
医療法人 きむら内科クリニック 理事長 木村 謙介

医療法人 きむら内科クリニック 理事長 木村 謙介
「病は気から」という言葉がありますが、すべてがそうであるとは言いません。医学的な知識や科学的な根拠は重要です。しかし、人の「心」の部分も同様に大切なものなのです。知識と心を同じ価値で考え、心身両面を同時に治療する。それが私の医療です。患者に限りなく関心を持ち、この人はいま何に一番心が捉われているのだろうかと考える。人の心にフォーカスして初めて真の医療が完成すると思っています。
医者になってから約20年間、大学病院で勤務医として働いていたのですが、そこでは病気自体にフォーカスして、病因に至る遺伝子や物質などの科学的な理由を探って解明しようとしていました。しかし、それでも治らずに繰り返し入院するというケースを多々経験するようになり、なぜそうなるのかということをずっと考えていました。同じ病名を付けられていても、患者によって経過が全く違う。それは「人間だから」なんですよね。一人ひとりがそれぞれ異なった環境、教育、文化の中で生まれ育っているので、それぞれに独特の考え方や心の使い方がある。そこから、患者自身の心の持ちようで病気の現象の表れ方が違うということに気づきはじめたのです。病気自体を診ることはもちろん大事です。私も医者として研鑽を積み、数々の論文も書いてきました。しかし、25年以上医師として臨床に携わってきた今、医療的知識や科学的根拠から病因を解明するだけでは不十分で、病気に至った患者の心の傾向性を把握し、それが背景にあるから病気になっているのだということをしっかりと抑えた上で、心身両面を治療することが何よりも大事であると考えています。それこそが真の医療なのではないでしょうか。これは医者にも一般の方々にも言えることですが、心の持ちようが直接病気にリンクしていることを理解していないがために的外れの診療となり、余計な検査をされたり、余計な薬を出されたり、挙句に治らないからと他の病院を紹介され、そこでも最終的に原因がわからなければ精神疾患と診断されて強い薬を処方されてしまう、そういう患者が世の中にはたくさんいます。逆に、私が話を聞いただけで、アドバイスをしただけで、薬を使うことなく病気が治ったということもよくあるのです。病気自体にフォーカスした医療だけではなく、「心」にフォーカスした医療も重要で必要なのだということを、より多くの人々に気付いてほしい。
病気になるということを皆ネガティブに捉えがちですが、病気は「メッセージ」であることが多いのです。たとえば、健康診断を受けた結果の数値が正常値を超えていたとする。それはすなわち生活習慣が乱れているから軌道を正しなさいというメッセージなのです。同じことが心においても言えて、人が何か不調を感じる時は、心の在り方が偏ってしまっている状態だということ。心の中道を保ちなさいというメッセージなのだと考えています。病気になったのは偶然ではなく、必ず理由があるということをポジティブに受け入れることが大事です。自分が病気になったことで健康であることの素晴らしさやありがたみを知り、病気というものを自分にとってプラスに変えようと思ったならば、その瞬間から心の在り方が変わっていきます。その先で、世の中のために、あるいは誰かを幸福にするために生きよう、そのためには自分が健康でなければならないという風に思いを変えていくのであれば、病気になったことは決してネガティブなことではなく、その人にとっては意義深い「学び」となっているはず。私が心身両面を同時に癒したいということの後ろには、病気は人生を好転させ、幸せになるチャンスだと捉えてほしいという思いがあるのです。
その考えを確信したのは、医師でもある妻が病気になったことでした。ALS(筋萎縮性側索硬化症)という原因不明の難病にかかり、7年ものあいだ闘病を続けています。今は人工呼吸器をつけており、自分で体を動かすことはできません。そんな妻を見ていて、これも必ず病気になった理由があるのだなと思うのです。妻の病気を機に大学病院を辞めて開業し、子育てと妻の介護をしながら、クリニックの立ち上げから軌道に乗るまで発展させてきたのですが、もし妻が病気になっていなければ、おそらくそのまま大学病院で働き続けており、私が今取り組んでいる心の医療は、まったく実現していなかっただろうと思います。私にもっとたくさんの人を救ってほしいという思いで、妻は自ら病気になることを受け入れて生まれてきたという考え方もあるわけです。そんなことは今の医学では誰も信じないし証明もできないからナンセンスだと切り捨てられますが、でも、私はそうは思わない。それを信じていく方がはるかにゆたかな人生を展開できると思っています。今後はこの心の医療への思いや考え方をより多くの人々に伝えていくために、メディアでの発信や執筆活動、国内外での講演活動を積極的に行っていこうと考えています。また、自分と同じような考えを持ってくれる医療従事者を育てていきたいという思いもあります。これがいちばん難しいところなのですが、心の医療が医学部の教育のカリキュラムのひとつに組み込まれれば、医師になる過程の早い段階で知識と心を同じ価値にすることができ、真の医療に近づくことができます。そのためにも今、臨床の中で取り組んでいる心の医療の科学的根拠を蓄えていくことが大事だと考えています。うちの病院に来てくれた患者さんには、何か一つでもプラスアルファになるような心に響く言葉を、あるいは元気をもらって帰ってほしいと思いますね。いつの日か心にフォーカスした医療が世界のスタンダードになるように、これからも日々の診療の一つひとつ、一人ひとりの患者さんを大切にしていきたいと思っています。

●2018年5月31日(木)
当院が、「頼れるドクター 小田急線 2018-19年版」の表紙に選ばれました!






●2018年4月3日(火)
「潜在意識を活かして健康生活を目指そう」

昨年に引き続き、片平中央クラブの定例会(於:片平会館)にて講演を行う機会を頂きました。今回のテーマは、「潜在意識」です。僕は以前から気になっていたことがありました。それは、健康診断の結果をお伝えするときに、生活習慣の改善について、毎年同じ人に、同じアドバイスを行っているということです。何故、毎年同じことを繰り返しているのだろうと。
フロイトやユングらの心理学者が、人間には、表面意識と潜在意識があることを発見しました。分かりやすく言えば、タテマエとホンネです。状況によって人の考えや判断は変わります。これが表面意識であり、タテマエの部分です。でも、潜在意識はそう簡単には変わらない、心に染み込んだホンネの部分です。健診で「もう少し痩せましょう」と言っても、「そうですよね。その方が健康に良いですよね」とタテマエで言います。でも、ホンネは「別に体型を気にしているわけじゃないし、困ってないからいいじゃないか」と思っていたら、結果は絶対に痩せないのです。
このホンネの部分、つまり「潜在意識」に良い考えを浸透させることが出来たなら、物事は良い方向に必ず進むはずです。タテマエとホンネを一致させることが出来れば、行為が習慣化して、疲れることなく結果を出すことが出来るのです。実に面白いことです。
今回の講演は、このあたりのメカニズムについて、お話ししました。

●2018年2月28日(水)
フォーラム・スバル(虹ヶ丘)で再び講演をさせて頂きました!

昨年の8月末の講演会でお伺いさせて頂いたフォーラム・スバル 友愛・健康の集い(於:ヴィラージュ虹ヶ丘)から再び講演の依頼を頂きました。前回、講演終了後に皆様から励ましのお声を沢山頂き、とても温かい人柄が印象的な地域です。今回は、「生涯現役人生を目指そう」というテーマで、前回を上回る約50名の方にご出席頂き、約1時間の講演とその後約15分間の質疑応答の楽しい時間を過ごすことが出来ました。企業や会社に定款や理念があるがごとく、個人にも、「目指すべき北極星」というべき、決してブレることのないポリシーや人生の目標が必要です。この目標が、出来るだけ「利他の精神」に根差していることが、様々な雑事に心を乱して、大切な時間を奪われることなく、身に起こる全ての出来事から何かを学んで向上するという常勝思考につながります。「生涯現役で生きる」ということは、「人生を爽やかに駆け抜ける」ということにほかなりません。多くの人達の支えがあって、ここまで生きてこられたことを感謝し、幾多の失敗や困難もかいくぐって、ここまで頑張ってきた自分に自信と誇りを持つこと。いくつになっても、学ぶべきことは残されていて、世間様にお返しすることも沢山ある。自分よりも若い人たちに希望を持たせるためにも、自分で自分を照らす人生を全うして、爽やかに生き抜いて欲しいというメッセージをお伝えしました。質疑応答では、病気があっても、それに執着せずに、「さらり」と受け入れて向上心を持ち続けるコツについてや、生涯現役で生きるために必要な楽天主義とは、意思をもって「ポジティブを選択する」ということであり、能天気とは違って「智慧」が必要であることをお伝えしました。集われた方々の放つ爽やかなオーラを感じることが出来、とても和やかな集いでした。ありがとうございました。

●2018年2月21日(水)
麻生区老人クラブ連合会にて基調講演「心で遺伝子を操作する」

これまでいくつかの地域老人クラブで講演させて頂き、お陰様で沢山の方々から好評の声を頂くことができました。今回、麻生区老人クラブ連合会という麻生区老人会の総本山(於:麻生区役所)において、講演の依頼を頂くことが出来ました。麻生区の9拠点の老人クラブの幹部の方々約45名の前で、「心で遺伝子を操作する」という演題でお話をさせて頂きました。
祖先から継承する動かしがたい宿命とも考えられている「遺伝や遺伝子」の概念に対して、「調節遺伝子」と言うスイッチをオンやオフに切り替える遺伝子が存在し、環境や外からの刺激によっても遺伝子による表現型を変更することが可能であるという知見を紹介しました。環境や外からの刺激とは、単に物理、化学的なものだけではなく、心の持ち方や感情ですら、遺伝子のスイッチを切り替えることが出来るという医学研究の結果を示しました。ヒトとチンパンジーやネズミは、遺伝子の数はそれほど変わらないのに、表現型は大きくことなります。この違いが、実はスイッチが入る場所やタイミングによって規定されているということの神秘をお伝えしました。遺伝子は細胞のひとつひとつの中に等しく内包されており、それが存在する場所の環境変化によって遺伝子のスイッチが切り替えられ、個性ある細胞へと変化します。一つ一つの細胞の在り方が、環境のいかんによって支配されるのなら、60兆個の細胞集団である我々人間も、同じではないかと考えます。細胞の一つの状態を決めるのが遺伝子そのものではないように、我々の人生も遺伝子で規定されているのではなく、その遺伝子にどんな環境や刺激を与えるかという意思が人生を決定すると考えられます。つまり、自分の周囲環境や、心のエネルギーである念いや考え方、情熱が遺伝子のスイッチを入れて人生を変えていくのだという趣旨のお話をさせて頂きました。少し、難しい話になりましたが、終了後に多くの方々から「素晴らしいお話でした」「もっと大きな会場でも話して欲しい」などとお声をかけて頂きました。

●2017年10月4日(水)
高齢者への講演会、第4弾は「生涯現役人生を目指そう!」

秋の深まる中、栗平白鳥自治会老人クラブの集会所において、第4回目の講演会を行いました。このクラブでは、熱意あるスタッフ達が、地域の高齢者の健康増進のため、様々な企画を立案、実行されております。今回は僕にお声をかけて頂き、講演をする機会に恵まれました。講演のタイトルは、「生涯現役人生を目指そう!」で、男女比4:28、平均年齢77歳の、32名の方に来て頂きました。医療などの発達で、日本人の平均寿命は年々伸び、21世紀中には100歳に到達することも予測されています。長生きすることが普通になる世の中で、「どうすれば、いつまでも、周りの人や世の中のお役に立てるような生き方が出来るのか?」という、質的に充実したな人生観を確立することがとても大切です。更にそれが仕事につながれば、高齢化に伴う介護や年金などの様々な社会問題をも解決する力になります。今回は、百寿者と云われる方々の実話や、科学的な根拠も交えて、生涯現役人生を目指すための心のティップをいくつかお話しさせて頂きました。講演後の茶話会では、皆さんの生の声を聞くことも出来ましたが、今回お集まり頂いた方は、既に様々なチャレンジをしておられる方が多く、とても勉強になりました。楽しく、充実した時間でした。有難うございました。

●2017年8月29日(火)
「すべての高齢者が持つべき考え方、真理を語る講演会」第3弾!!!

残暑の厳しい中、フォーラム スバル 友愛・健康の集い(於:麻生区虹ヶ丘団地集会所)において、第3回目の講演会を行いました。フォーラム スバルでは、これまでも何度か医療者を講師に招いて講演会を開いておられ、健康・長寿に熱心な高齢者が集っております。今回は、男女比14:11で平均年齢77.6歳の25名の方に来て頂きました。テーマは、僕のライフワークでもある、「あの世」の存在を様々な切り口からお伝えするという内容です。「人間の本質は肉体ではなく、心なのだと。この世では肉体は必要なので、当然、身体の手入れは大切だけど、あの世に持ち帰れるものは心だけなので、最後はあまりこの世や肉体に執着せず、持ち帰るべき心をしっかり磨いて、明るく輝いて生きて行きましょう」というメッセージを熱くお話ししました。
講演後のアンケートでは、講演前には「あの世」を信じている人は17名でしたが、講演後は24名が信じると回答され、講演がこれからの生き方に良い影響を与えると答えた方が22名、元々「あの世」は信じていたので、生き方はこれまで通り変わらないと回答された方が3名でした。
アンケートに記載して頂いた受講者の声として、
「私は、先生と同じ意見を持っています」
「久しぶりに良いお話し、有難うござました」
「先生のようなお考えの医師は殆どいないと思います。以前から先生のお考えのような医師に向き合いたいと思っていましたが、皆無でした」
「清々しい気持ちになりました。感謝申し上げます」
「考えが変わりました」
「私の病院の先生とは全く違うと思った」
「私も以前から、永遠の生命を信じていました。今日は本当に、本当にありがとうございました」
「人を許すことを学びました」
「これからの生き方が非常に楽しくなりました」
「非常に神秘的な話でした。参考になりました。有難うございます」
「他人のために尽くすことが自分の幸福になると思い生きてきました。これからも心をみがいて参ります」
「日野原重明先生も同じような考えだったと思えました。」
「講演を聞いて、なんだか元気をもらったような、少し笑顔になったような気がします」
「先生のお話し、本当に心から感謝致します」
心を変えて生きることの大切さを、今回も高齢者の皆さんから学びました。講演を終わった後の握手攻め!皆さんの笑顔がとても嬉しく、こちらがパワーを沢山もらって帰って来ました。
次回は、10月に2件、別の老人クラブで講演する予定です。

●2017年6月1日(木)
腸から健康を目指す!
ヒトの腸内には、約100兆個の腸内細菌が存在していると言われています。単一の細菌ではなく、腸の内容物1gあたり、実に500種類以上の細菌が存在します。最近、この腸内細菌の集団(腸内細菌叢あるいは腸内フローラと呼ばれる)が、ヒトの健康維持や病気の発生に大きく関わっていることが解明されてきました。ヒトの全細胞数が約37兆個ですから、もはやこの100兆個を無視するわけにはいきません。ヒト全体の身体の働きを理解する場合に、ヒト自身の細胞だけではなく、腸内細菌などのヒトに常在する菌とのやりとりを含めた統合的な理解が必要となります。これを、「superorganism (超生命体)」と言います。
我々が食事をすると、小腸から低分子化合物と言われるグルコースやアミノ酸が吸収されます。そこで吸収されなかった未消化物は、大腸に送られ、腸内フローラと言われる細菌集団の餌となり、細菌によって代謝されて、その代謝物質が腸管上皮細胞から吸収され、血管を介して全身に分配されます。 腸内細菌の中には、酢酸や乳酸、酪酸などの良い代謝物を産生する善玉菌もいますが、デオキシコール酸、トリメチルアミン、尿毒素などの発癌や動脈硬化などの原因になる有害物質を産生する悪玉菌もいます。つまり、そのヒトが、どんな腸内フローラを持っているかということが、健康維持や病気の発生に大きな影響を及ぼすのです。
100兆個も存在するヒトの腸内フローラは、“門”という4つの種族(バクテロイデス門、ファーミキューテス門、アクチノバクテリア門、プロテオバクテリア門)に分類され、“門”の下に、さらに“属”など、非常に細かく分類されています。善玉菌の代表であるビフィズス菌は、アクチノバクテリア門に属していますが、“門”は、善玉菌、悪玉菌を単純に分類したものではありません。例えば、悪玉菌の代表であるウェルシュ菌は、ファーミキューテス門に属しますが、善玉菌の乳酸菌の一種もここに属しています。
同じ物を食べ続けていても、同一個人で腸内フローラを構成する細菌の種類や割合は、年齢と伴に変化します。また、同じくらいの年齢で、同じ地域で、だいたい同じような物を食べている場合には、腸内フローラの傾向性は似ていることがありますが、全く同一と言うことは通常はありません。同一個人で、腸内フローラが悪い方向に変化する要素として考えられているのは、偏った食事(脂肪食)、暴飲暴食、ストレスや過労、抗生剤などの薬、細菌感染、加齢、気候や温度などです。ちなみに、人工甘味料のとりすぎは、腸内フローラを変化させ、糖尿病を悪化させることが報告されています。
これまでの研究で、腸内フローラが乱れる(悪玉菌が優勢になる)ことが原因となって発症する病気として、大腸炎や大腸癌、肝臓癌、肥満、糖尿病、動脈硬化の他、免疫異常や喘息などのアレルギー疾患などが知られています。意外なことに脳に関する病気(自閉症や行動異常、ストレス耐性、多発性硬化症など)も関連が報告されており、“脳―腸連関”と呼ばれています。脳と腸は、自律神経を介してネットワークがつながっているのです。
個人ごとに異なる腸内フローラですが、それではいったい、どうすれば善玉環境を維持することが出来るのでしょうか?ヒントは、さきほど記しました、腸内フローラが悪い方向に変化する要素の逆をすれば良いと言うことになります。食事は特に重要です。何故なら、我々が食べたものこそが、腸内フローラを構成する細菌達の餌になるのですから。
腸内環境を改善する可能性のある食品としては、
① 食物繊維(海草、根菜類、雑穀、きのこ類、果物、オリゴ糖など)
② ヨーグルト(ビフィズス菌、乳酸菌)
③ 発酵食品(納豆、キムチ、糠漬けなど)
ですが、これらの食品を「たまに食べる」では腸内フローラは変わりません。長期的な食習慣として、上記の食品を、毎日意識して取り入れたいものです。
ヒトの腸内には、約100兆個の腸内細菌が存在していると言われています。単一の細菌ではなく、腸の内容物1gあたり、実に500種類以上の細菌が存在します。最近、この腸内細菌の集団(腸内細菌叢あるいは腸内フローラと呼ばれる)が、ヒトの健康維持や病気の発生に大きく関わっていることが解明されてきました。ヒトの全細胞数が約37兆個ですから、もはやこの100兆個を無視するわけにはいきません。ヒト全体の身体の働きを理解する場合に、ヒト自身の細胞だけではなく、腸内細菌などのヒトに常在する菌とのやりとりを含めた統合的な理解が必要となります。これを、「superorganism (超生命体)」と言います。
我々が食事をすると、小腸から低分子化合物と言われるグルコースやアミノ酸が吸収されます。そこで吸収されなかった未消化物は、大腸に送られ、腸内フローラと言われる細菌集団の餌となり、細菌によって代謝されて、その代謝物質が腸管上皮細胞から吸収され、血管を介して全身に分配されます。 腸内細菌の中には、酢酸や乳酸、酪酸などの良い代謝物を産生する善玉菌もいますが、デオキシコール酸、トリメチルアミン、尿毒素などの発癌や動脈硬化などの原因になる有害物質を産生する悪玉菌もいます。つまり、そのヒトが、どんな腸内フローラを持っているかということが、健康維持や病気の発生に大きな影響を及ぼすのです。
100兆個も存在するヒトの腸内フローラは、“門”という4つの種族(バクテロイデス門、ファーミキューテス門、アクチノバクテリア門、プロテオバクテリア門)に分類され、“門”の下に、さらに“属”など、非常に細かく分類されています。善玉菌の代表であるビフィズス菌は、アクチノバクテリア門に属していますが、“門”は、善玉菌、悪玉菌を単純に分類したものではありません。例えば、悪玉菌の代表であるウェルシュ菌は、ファーミキューテス門に属しますが、善玉菌の乳酸菌の一種もここに属しています。
同じ物を食べ続けていても、同一個人で腸内フローラを構成する細菌の種類や割合は、年齢と伴に変化します。また、同じくらいの年齢で、同じ地域で、だいたい同じような物を食べている場合には、腸内フローラの傾向性は似ていることがありますが、全く同一と言うことは通常はありません。同一個人で、腸内フローラが悪い方向に変化する要素として考えられているのは、偏った食事(脂肪食)、暴飲暴食、ストレスや過労、抗生剤などの薬、細菌感染、加齢、気候や温度などです。ちなみに、人工甘味料のとりすぎは、腸内フローラを変化させ、糖尿病を悪化させることが報告されています。
これまでの研究で、腸内フローラが乱れる(悪玉菌が優勢になる)ことが原因となって発症する病気として、大腸炎や大腸癌、肝臓癌、肥満、糖尿病、動脈硬化の他、免疫異常や喘息などのアレルギー疾患などが知られています。意外なことに脳に関する病気(自閉症や行動異常、ストレス耐性、多発性硬化症など)も関連が報告されており、“脳―腸連関”と呼ばれています。脳と腸は、自律神経を介してネットワークがつながっているのです。
個人ごとに異なる腸内フローラですが、それではいったい、どうすれば善玉環境を維持することが出来るのでしょうか?ヒントは、さきほど記しました、腸内フローラが悪い方向に変化する要素の逆をすれば良いと言うことになります。食事は特に重要です。何故なら、我々が食べたものこそが、腸内フローラを構成する細菌達の餌になるのですから。
腸内環境を改善する可能性のある食品としては、
① 食物繊維(海草、根菜類、雑穀、きのこ類、果物、オリゴ糖など)
② ヨーグルト(ビフィズス菌、乳酸菌)
③ 発酵食品(納豆、キムチ、糠漬けなど)
ですが、これらの食品を「たまに食べる」では腸内フローラは変わりません。長期的な食習慣として、上記の食品を、毎日意識して取り入れたいものです。

●2017年5月31日(水)
「頼れるドクター 小田急線 2017-2018版」の掲載記事


●2017年5月20日(土)
当院も参加した「夜間高血圧管理の重要性」に関する研究の結果
当院でも、10数名の患者様にご協力頂いた、夜間高血圧管理の重要性を調査した臨床研究の結果が報告されました。
夜間高血圧は、心血管病の危険因子であることが知られています。通常であれば、血圧は、日中に比べて睡眠中は低下しますが、降圧剤を服薬していても、夜間の血圧の低下が乏しいか、逆に日中より上昇している場合があり、心血管病のリスクが高まります。背景には、睡眠時無呼吸症候群や不眠症などの睡眠障害が隠れている場合もありますが、塩分の摂りすぎなどによる循環血液量の増加も原因のひとつと考えられています。
当院でも、10数名の患者様にご協力頂いた、夜間高血圧管理の重要性を調査した臨床研究の結果が報告されました。
夜間高血圧は、心血管病の危険因子であることが知られています。通常であれば、血圧は、日中に比べて睡眠中は低下しますが、降圧剤を服薬していても、夜間の血圧の低下が乏しいか、逆に日中より上昇している場合があり、心血管病のリスクが高まります。背景には、睡眠時無呼吸症候群や不眠症などの睡眠障害が隠れている場合もありますが、塩分の摂りすぎなどによる循環血液量の増加も原因のひとつと考えられています。
今回は、夜間の時間を設定して血圧測定が可能であり、計測値が無線で送信出来る新しく開発された血圧測定装置を用いました。アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)という降圧薬1剤の服薬でも十分な降圧効果が得られなかった患者様を対象に、2種類の降圧剤(ARB+カルシウム拮抗薬(CCB)の合剤か、ARB+サイアザイド系利尿薬(D)の合剤)のうちのどちらかを無作為に服薬して頂き、どちらが有効であるかを、当院の患者様を含め、全国の411名の患者様を対象に、夜間血圧の低下とそれが及ぼす心臓や腎臓への保護効果について調べた結果です。
結論として、いずれの薬剤を用いても3カ月後の夜間の血圧は低下しましたが、ARB+CCBを用いた群の方が、より夜間血圧を低下させました。ただし、高齢者、腎機能障害や糖尿病が合併するとARB+CCB群とARB+D群の差はほとんどみられませんでした。夜間血圧がしっかり低下した群では、心臓や腎臓の機能に関する血液や尿の検査データがより改善しました。
この研究の結果からは、夜間血圧をしっかりコントロールすることが、心血管病を防ぐために非常に重要と考えられました。
当院では、今回の臨床試験に用いたものと同じ血圧計を利用して、夜間血圧を測定して頂くことが可能です。日中の血圧が良好でも、夜間高血圧を放置すると、動脈硬化や心血管病発症のリスクにつながるため、測定を希望される方はご来院下さい。

●2017年5月6日(土)
「高齢者に希望をもって生きて頂く」ための講演会 第2弾!!
ゴールデン・ウィーク最中の5月6日(土)、地域老人会(はるひ野シニアクラブ)の総会(於:はるひ野小学校内の地域交流センター)において、第2回目の講演会を行いました。演題は、前回と同じ「人生の先輩達に伝えたいこと」で、平均年齢79歳の18名の会員の方に聴いて頂きました。
今回は、第1回目の講演会での気付きから、僕自身の経験を踏まえた具体例を更にいくつか取り上げて約1時間、お話しさせて頂きました。
講演後のアンケートでは、講演前に「あの世を信じる」と考えていた8名の方が、講演後には15名に、講演前に「あの世を信じない」と考えていた3名が、講演後には0名になり、「この講演がこれからの生き方に良い影響を与える」と答えた方が全員の18名という嬉しい結果でした。
アンケートに記載して頂いた受講者の声として、
「とてもいいお話しを有難うございました。家族ともに聴けたらと思いました」
「自分の両親が愛情に溢れた素晴らしい人生の先輩でしたので、自分ももう少し周囲の人達に愛を注ぐ努力をしたいと思いました」
「魂の連続性に強く感動しました」
「先生のような人から、何回もお話しを聞きたいです」
高齢者の心を変えることこそが、真に「希望をもって生きて頂く」ことに繋がると信じています。
「死」を真正面から見据えても決して動じない「不動心」を得て頂くことが、この講演活動の目的です。
ゴールデン・ウィーク最中の5月6日(土)、地域老人会(はるひ野シニアクラブ)の総会(於:はるひ野小学校内の地域交流センター)において、第2回目の講演会を行いました。演題は、前回と同じ「人生の先輩達に伝えたいこと」で、平均年齢79歳の18名の会員の方に聴いて頂きました。
今回は、第1回目の講演会での気付きから、僕自身の経験を踏まえた具体例を更にいくつか取り上げて約1時間、お話しさせて頂きました。
講演後のアンケートでは、講演前に「あの世を信じる」と考えていた8名の方が、講演後には15名に、講演前に「あの世を信じない」と考えていた3名が、講演後には0名になり、「この講演がこれからの生き方に良い影響を与える」と答えた方が全員の18名という嬉しい結果でした。
アンケートに記載して頂いた受講者の声として、
「とてもいいお話しを有難うございました。家族ともに聴けたらと思いました」
「自分の両親が愛情に溢れた素晴らしい人生の先輩でしたので、自分ももう少し周囲の人達に愛を注ぐ努力をしたいと思いました」
「魂の連続性に強く感動しました」
「先生のような人から、何回もお話しを聞きたいです」
高齢者の心を変えることこそが、真に「希望をもって生きて頂く」ことに繋がると信じています。
「死」を真正面から見据えても決して動じない「不動心」を得て頂くことが、この講演活動の目的です。

●2017年4月24日(月)
新百合ヶ丘総合病院との糖尿病における病診連携への取り組み
当院では2017年4月より糖尿病内科を標榜し、患者様に安心して受診して頂ける体制を整えております。
近隣の中核病院である新百合ヶ丘総合病院とも、病診連携の体制を整えたいと、キックオフ・ミーティングに参加致しました。
食事、運動などの糖尿病教育目的や血糖コントロール不良時等に受診、入院して頂けるように、医師同士が顔の見えるお付き合い
をしておくことも重要だと考えております。
当院では2017年4月より糖尿病内科を標榜し、患者様に安心して受診して頂ける体制を整えております。
近隣の中核病院である新百合ヶ丘総合病院とも、病診連携の体制を整えたいと、キックオフ・ミーティングに参加致しました。
食事、運動などの糖尿病教育目的や血糖コントロール不良時等に受診、入院して頂けるように、医師同士が顔の見えるお付き合い
をしておくことも重要だと考えております。

●2017年4月4日(火)
”一風変わった講演”としてタウンニュース誌に紹介された「高齢者の生き方」を変える斬新な取り組み(関連記事参照)
2017年4月4日(火)に、地域老人会(片平中央クラブ)の定期集会(於:片平会館)において、「人生の先輩達に伝えたいこと」と題して講演会を行いました。
医者が高齢者に話すというと、「如何にして健康長寿を目指すか?」という内容で、食事や栄養、運動や体操、趣味や社会活動などへの参加を推奨するのが一般的です。
けれど、最後に死が待ち受けている事実は動かしようがなく、日本人の平均寿命の80代を迎えた高齢者の潜在意識では「いよいよ最終コーナーを曲がった」と考え、心の奥底でごくりと生唾を飲んでいます。
“お笑い”で、つかの間の現実逃避をしてみても、「死」に対する確固たる考え方が定まっていなければ、再び現実に向き合った時に、精神的に安定性を保つことは難しいと考えます。
万人に必ず訪れる死に対して、どのように向き合えば、歳をとっても希望を抱いて生きることが出来るのか?これは“サイエンス”の世界では決して解明できません。
“サイエンス”を追求している研究者自身ですら、いずれはこの問題に自らが直面する訳ですが、彼らが答えを持っているとは到底考えられません。
今回の講演会はひとつの挑戦でした。
“医者”が「あの世」の存在を肯定し、それを信じることを勧め、どんなに年老いても未来への希望を失わずに生きることを公に語った訳ですから。
原理はとてもシンプルです。
「あの世」の存在を信じていたのに、死んでみたら何も無くなったとしても、痛くも痒くもない。
けれど、「あの世」などあるわけないと、大した根拠もないのに信じこんでいて、結局「あの世」があってしまったら、驚きのあまり右往左往するだろうということです。
ですから、「あの世」はあると信じていた方が良いに決まっているのです。
そのうえで、如何に生きるかということを考えた時に驚くべきパワーが生まれます。
講演の結果は、大成功でした。
44名の聴衆に対するアンケート調査で、講演前に「あの世を信じない」と考えていた7名の人が、講演後には0名になり、40名の方が、「講演が今後の生き方に良い影響を与える」と回答したのですから。
僕はこの活動をライフワークとして発展させていこうと考えています。
講演会を希望される老人会などの方は是非、クリニックに御連絡下さい。
2017年4月4日(火)に、地域老人会(片平中央クラブ)の定期集会(於:片平会館)において、「人生の先輩達に伝えたいこと」と題して講演会を行いました。
医者が高齢者に話すというと、「如何にして健康長寿を目指すか?」という内容で、食事や栄養、運動や体操、趣味や社会活動などへの参加を推奨するのが一般的です。
けれど、最後に死が待ち受けている事実は動かしようがなく、日本人の平均寿命の80代を迎えた高齢者の潜在意識では「いよいよ最終コーナーを曲がった」と考え、心の奥底でごくりと生唾を飲んでいます。
“お笑い”で、つかの間の現実逃避をしてみても、「死」に対する確固たる考え方が定まっていなければ、再び現実に向き合った時に、精神的に安定性を保つことは難しいと考えます。
万人に必ず訪れる死に対して、どのように向き合えば、歳をとっても希望を抱いて生きることが出来るのか?これは“サイエンス”の世界では決して解明できません。
“サイエンス”を追求している研究者自身ですら、いずれはこの問題に自らが直面する訳ですが、彼らが答えを持っているとは到底考えられません。
今回の講演会はひとつの挑戦でした。
“医者”が「あの世」の存在を肯定し、それを信じることを勧め、どんなに年老いても未来への希望を失わずに生きることを公に語った訳ですから。
原理はとてもシンプルです。
「あの世」の存在を信じていたのに、死んでみたら何も無くなったとしても、痛くも痒くもない。
けれど、「あの世」などあるわけないと、大した根拠もないのに信じこんでいて、結局「あの世」があってしまったら、驚きのあまり右往左往するだろうということです。
ですから、「あの世」はあると信じていた方が良いに決まっているのです。
そのうえで、如何に生きるかということを考えた時に驚くべきパワーが生まれます。
講演の結果は、大成功でした。
44名の聴衆に対するアンケート調査で、講演前に「あの世を信じない」と考えていた7名の人が、講演後には0名になり、40名の方が、「講演が今後の生き方に良い影響を与える」と回答したのですから。
僕はこの活動をライフワークとして発展させていこうと考えています。
講演会を希望される老人会などの方は是非、クリニックに御連絡下さい。